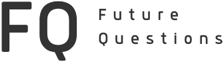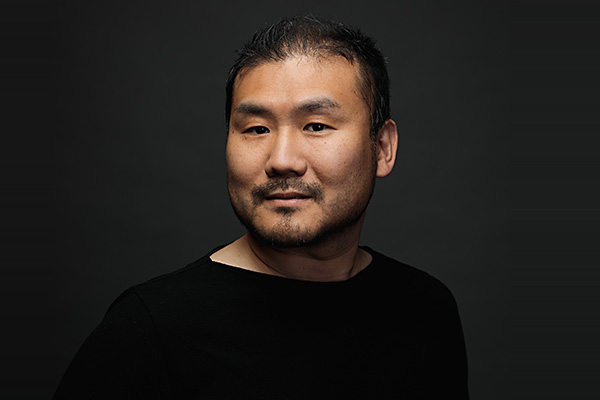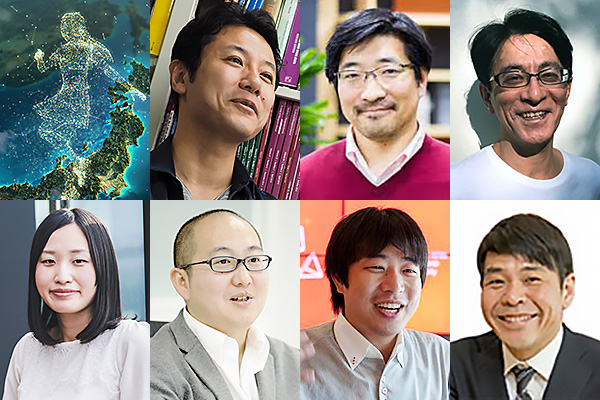2019.07.12.Fri
文化庁メディア芸術祭
Future Questionsイベントレポート「アートから見る未来とは」
「アートから見る未来とは」の問いをテーマに掲げた、Future Questions(FQ)のオリジナルイベントが開催された。今回、FQイベントの舞台となったのは日本科学未来館イノベーションホール。文化庁メディア芸術祭の最終週である6月15〜16日の2日間、FQ×メディア芸術祭のコラボ・イベント「Future Questions SESSIONS〜アートから見る未来とは〜」として行われた。
イベントでは、Yahoo! JAPANによる初のアート『Contextual Studies』が両日に渡り展示。また特別プログラムとして、アーティストSeihoによる前衛的なサウンドパフォーマンスと、メディアアーティスト市原えつことアーティスト草野絵美のトークセッション「AI時代における、“したたかアーティスト“の生き方」を実施。それぞれ異なる角度から「アートから見る未来とは」の問いについて表現――ここでは、その模様をレポートしたい。
Yahoo! JAPANのメディアアート作品『Contextual Studies』


Yahoo! JAPANに在籍するデザイナー、サイエンティスト、メディアアーティストによって開発され、社外でのアート作品展示としては初の試みであった。この作品『Contextual Studies』のコンセプトには、"インターネットが一般化し情報が飽和する現代において、前後の文脈に関係なく立ち上がるコンテクストに着目。私たちが無意識に行っている情報の取捨選択との向き合い方を問いかける"とある。長きにわたり日本のインターネット市場の中心にある企業として、「アートから未来を思考する」問いを可視化させた独自のインスタレーションだ。
この作品の中枢にあるのは、Yahoo!知恵袋に寄せられた無数のワード。そのひとつひとつのワードが、前後の文脈に関係なく一定のルールで集合・離散を繰り返すというもの。不規則に現れる数々のワードには、非常にストレートで欲求を感じるもの、時節・時代のトピックスを感じさせるものなどさまざまで、誰かがーーいやもしかしたら自らが問いたかもしれないという気持ちになり夢中でワードを追いかけてしまう。
来場者のなかでも、『Contextual Studies』の空間に長くたたずむ人たちが多く見受けられ、個人が情報に向き合う特別な体験となったのではないだろうか。
未来を構想するための「問い」、サウンドパフォーマンスSeiho

Seiho(アーティスト)
森崎進(作家)
花井裕也/上條慎太郎/浅井裕太/石井達哉/毛利恭平/竹村佳保里[Rhizomatiks]
Yohsuke Chiai(Visual Designer)/Takuma Nakata(Visual Designer)/Taro Mikami(Producer)[Visual Production CEKAI]
サウンドパフォーマンスとして登場したアーティストSeiho。彼は、今年3月15日に行った非公開イベント< 靉靆(あいたい)>を皮切りに、"音楽ライブ" の可能性を追求し続けている。そして今回、この日限りのプログラム、CEKAIによる映像と、Rhizomatiksのテクニカルサポートのもと、未来を構想するための「問い」を表現してくれた。

この日、Seihoはテーブルに座りひたすら食事をした。目を覚ましてから再び眠りに落ちるまで、ワインを飲み、パンをかじり、サラダを食べて、またワインを飲み、時に考えごとをし、読書をし、ワインを飲み干すーー時間にして40分間、このループが何回続いただろうか。この状況を補足すると、Seihoが座るセットはまるで書斎のようで、彼自身はスーツに身を包んでいる。そして執事が現れ、彼にワインやパンをサーブする。これもループのなかで同じように行われるのだ。このセットの背景には大きなスクリーンがあり、複数台設置されたカメラによって、食事をするSeihoの様子をリアルタイムで録画した映像が映し出されていく。そしてうごめくような低いビート、ノイズが敷かれた上にファドがサンプリングされた楽曲が重なり、これもひとつのループに括られている。


「いったい何が起きているのだろう?」――会場にいるオーディエンスの誰もがおなじことを思ったのではないだろうか。ただ、このループを見ているうちに気づくことがある。いま、目の前で食事をしているSeihoと、スクリーンのなかで食事をしているSeiho。何かが違う。そう、繰り返し食事をするSeihoが蓄積されていったような、スクリーンのなかにいるSeihoは"いま"と"過去"で食事をしているのだ。




この作品には、見えている"いま"があり、そして"過去"がある。同じループを数えるあいだに"未来"も見えてくる気がする。なんとも言えない奇妙な感覚はループが重なるごとに増し、あるときプツリとループが終わりステージは幕を閉じた。パフォーマンスが終わったあと数秒間、オーディエンスそれぞれが余韻にひたるかのように沈黙をし、そのあと大きな拍手とともに現実の世界に引き戻された。
過去や未来、その時間という概念をどう捉えるのかーー答えはきっとない。目にしたおのおのにある記憶だけが事実として残る、強烈な"問い"であると感じた。
最後に、来場者にむけて会場で配られた文章を紹介したい。
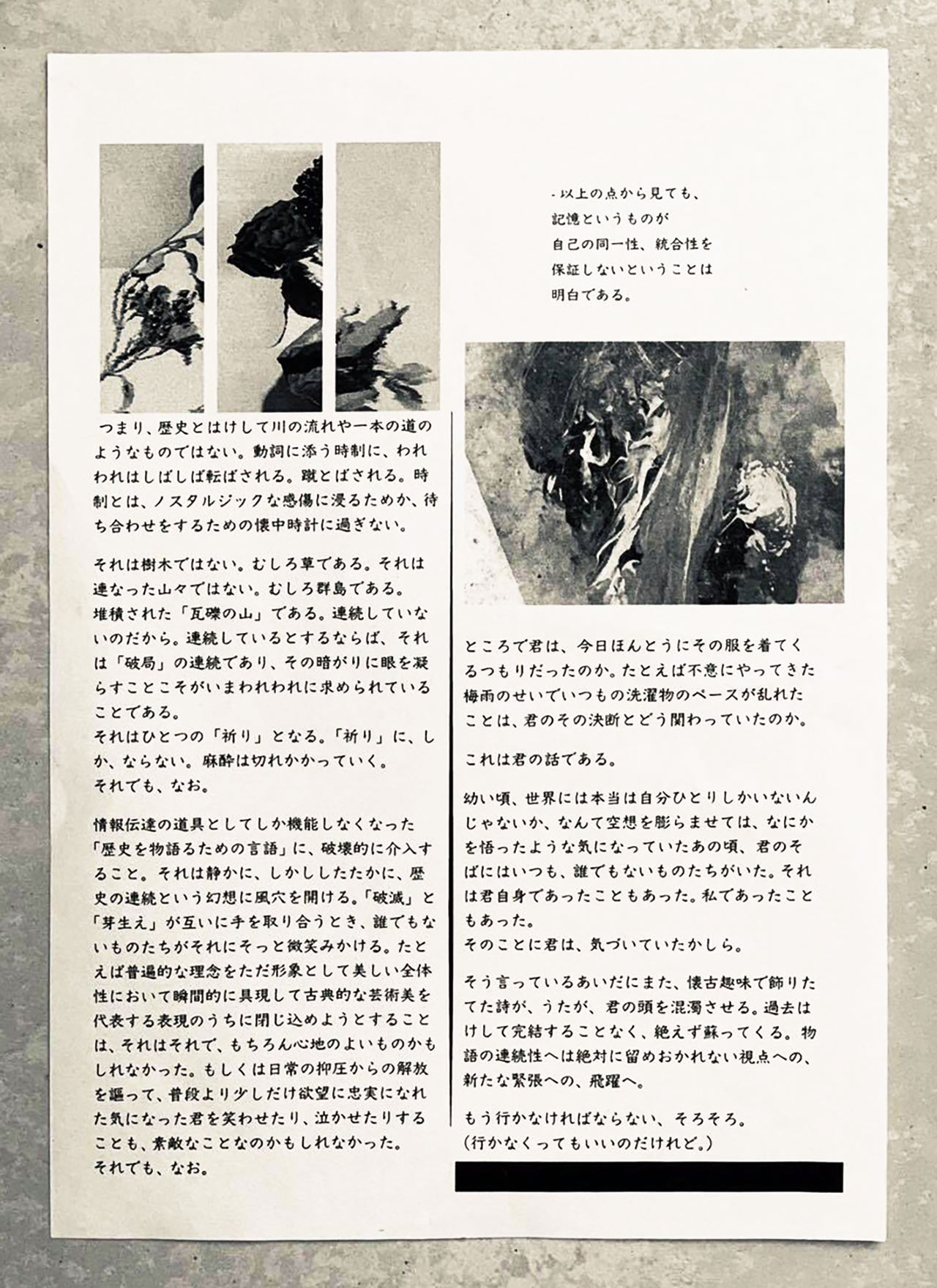

TALK SESSION市原えつこ×草野絵美「AI時代における"したたかアーティスト"の生き方」
特別プログラムの後半に行われたトーク・セッションでは、市原えつこ(メディアアーティスト、妄想インベンター)と草野絵美(アーティスト、タレント)のお二人が登場。モデレーターとして水田千恵(Yahoo! JAPAN)が立ち、「ビジネス×アート」、「したたかアーティストの生き方」、「アート・テクノロジーについて」の三つのテーマを軸にトークが展開された。
アーティストが考える「ビジネスとアート」

ひとつめのテーマは「ビジネスとアート」。市原と草野は企業とアート作品を作っていく意義をどう考えているのだろうか。
草野「私は広告業界にいたのですが、旧来の宣伝というものが意味をなさなくなった時代に、企業という"人格"が独立して見せられるもの、それがアートだと思うんです。生き様としてアート作品を発信するということはこれから重要になってくるでしょうね」
人の心に刺さる表現――綺麗ごとではない発信にはある種の変態性や属人性などアートの強さが求められる。
市原「とは言いつつも企業コラボ案件はお互いの思いやりが大事ですよね(笑)。やはり時たま事故が発生する事例もあるんですよ。企業はコンプライアンスや株主の意向も守らなきゃいけない。でもアーティストはまた別の論理で動いてるから。例えば私の場合は『セクハラ・インターフェース』など性的な作品や、死に関する作品は炎上する可能性もあるから、いかにポップでまろやかにコーティングして出すか、企業案件では常にバランスを考える必要がありますね」
セクハラ・インターフェース(喘ぐ大根)
草野の言葉を借りると「ひねくれマインド」。一見、企業利益に反しそうなアーティストとしての表現を作品の完成度で凌駕する。そして市原が話す「バランス」もアート表現の一部であり、その心意気を持ってアートをビジネスとして成立させる。ビジネスとアートの懸け橋となる部分には、こうしたアーティストの発想力とそれを受けとるビジネス側のマインドセットも必要であると感じた。

草野絵美(アーティスト、タレント)
したたかアーティストの生き方
ふたつめのテーマにある"したたか"という際どいキーワード、来場者もこのテーマには興味深そうに聴き入っていた。
市原「必ずしもアーティストは純粋な存在じゃないと私は考えていて、単純に作りたいものだけ作るだけだと立ち行かないことも多い。今回のトークテーマとして『したたかアーティスト』というキーワードが生まれてきたのは、作品を作ったときに、どうやってメディアに乗せてプロモーションをするかという広報的な戦略も作家本人が戦略を立ててやっていたりするし、資金調達も含めて、一人広告代理店みたいなところがあります」
草野「やりたいことがわかっているだけでも協力者を集めやすいというのはあります。今回、Satellite Young(草野が活動する音楽ユニット)の新曲『新世界Banzai』は映像も自分で作ったんですが、私たちは海外のアーティストとコラボする機会が多いのですが、このときは、上海のルー・ヤンというニューメディア・アーティストが、上海の展示会場内の中での撮影を勧めてくれたことで、実現しました」
Satellite Young - New World Banzai / 新世界Banzai (Official Video Collaboration with Lu Yang)
草野がルー・ヤンの作品に感動した旨のメッセージをFacebookから送ったことで、つながりができ、ルー・ヤンの上海ビエンナーレの展示にSatellite Youngの音楽を全編で使用。日本の音楽市場よりロンドンやLAでSpotifyの再生回数が上位に入っているという。他にもスウェーデンのYouTuberと組んで曲をローンチするなど、日本人以上に80'sのシンセ歌謡が海外でフィットした事実がうかがえる。
草野「私、飽きっぽいんで戦略としてアーティストって名乗ってるところがあって。ミュージシャンとして活動するんですけど、MVを自分で作ってみたり、声優をしているアニメーションもある。ですが、それら全部がSatellite Youngってテーマをもってできるんです。一貫して好きなのはテクノロジーと人間の関わりなので、テイストさえ同じにしておけば表現媒体は変えられる。何より作り続けないのが嫌なので」

したたかアーティストは「資金調達をどこに求めるか?」も、自分のアートの本質につながる要素だという。
市原「お金って色があるんだなと最近つねづね実感しています(笑)。『デジタルシャーマン・プロジェクト』は文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業(平成27年度)で支援いただいて、専門家によるメンタリングまでいただける上にアーティストの表現の自由度が高い資金でした。でも企業とのコラボレーション案件やスポンサードでいただくお金でやるプロジェクトは、株価に悪影響を与えてしまったらアウトだし、広範囲への配慮が必要なお金ですよね。でも、そういう時は企業さんのプロモーションと自分の欲望をいかにうまく融合させるかが作家の腕の見せどころだと思います」
デジタルシャーマン・プロジェクト
市原そして草野がおなじく語っていたこととして、"アーティスト自身のキャラクターも大事"。理由として、個人のメディアアーティストを知らない代理店も意外と多いそうだ。そこで作品と作った人のパッケージ感でプロモーションすることが有効だというわけだ。

市原えつこ(メディアアーティスト、妄想インベンター/第20回メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞)
テクノロジーとアート制作の今後
最後のテーマは今回のセッション全体にかかる「AI時代における、"したたかアーティスト"の生き方」の核心部分。テクノロジーが生活に融合する中で、アーティストはどう変化し、世界でサバイブしていくのか?という問いかけだ。
市原「これからはたぶん、複数のツールを組み合わせてアーティストは指揮者みたいに作品を制作していって、一人あたりでまわせるプロジェクトの規模は大きくなるとは思うんですね。だからこれからはむしろ初期衝動をいかに忘れないようにするかが大切だと思っていて。私は、たまにインタビューのお仕事もさせていただくのですが、だいたいアーティストには"世間的には立派ではないけど、それでもやっちゃうこと"が幼少期とかにあって、でもそこがその人の本質で、魅力だと思う」
草野「Adobeプレミアを使って、ミュージックビデオを自分で編集したんですけど、すごく進化してて、数年後には作業が半分ぐらいになっちゃうんじゃないかなと思ったんです。だからAIに駆逐される部分は必ずあるから、代替できない自分のバリューみたいなところを可視化して、言語化することがすごく重要な気がします」

市原は、インターネットにより興味がつながる縁が増えていったからこそ、次は土着の縁に回帰しようと、東京で奇祭を行うことを画策中だという。そこはもちろん、市原が募るアノニマスな人々により、その土地に仮想通貨を奉納するという、アーティスティックなシナリオが仕込まれているらしい。それは回帰なのか未来なのか?
テクノロジーやツールが進化することで、より人の存在がフォーカスされていくと語る二人。テクノロジーの進歩はアーティストにも色濃く影響を与えている。
今回のパフォーマンスやトークで、その実感がさらに深まったのではないだろうか。
- 取材・文・写真:宍戸麻美、石角友香
- 編集・取材:Qetic(けてぃっく)
- 国内外の音楽を始め、映画、アート、ファッション、グルメといったエンタメ・カルチャー情報を日々発信するウェブメディア。メディアとして時代に口髭を生やすことを日々目指し、訪れたユーザーにとって新たな発見や自身の可能性を広げるキッカケ作りの「場」となることを目的に展開。
https://qetic.jp/(外部サイト)
#04 アートは未来をどう変える?
-
- Chim↑Pomインタビュー
- 理屈のつかない面白さが、一線を飛び越える力になる
- 2019.06.14.Fri
-
- Ars Electronica 小川秀明インタビュー
- 「人間らしさを問う」アートシンキングの可能性
- 2019.07.12.Fri
-
- 宇川直宏インタビュー
- いま、メディアのアイデンティティが試されている。DOMMUNEのアティテュード
- 2019.07.12.Fri
-
- アートから見る未来
- 未来を想像させ、問いを与える「社会実装されるアート」
- 2019.07.31.Wed
-
- 5人の選者による
いま見られる アート 10作品 - 2019.06.14.Fri
-
- 文化庁メディア芸術祭
- Future Questionsイベントレポート
「アートから見る未来とは」 - 2019.07.12.Fri
-
- イベントレポート
- 「人工知能は人を感動させられるのか?」
- 2019.07.31.Wed