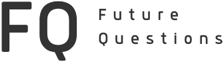2020.06.23.Tue
齋藤精一インタビュー
withコロナ時代、都市はどう変わる? 人間の延長上にある都市づくりへ
【#コロナとどう暮らす】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため各地で緊急事態宣言が発令され、都市から人が消えた。新しい生活様式が求められる中で、人々にどのような変化が芽生えたのか。withコロナ時代、都市のあり方はどう変わるのか。ライゾマティクス・アーキテクチャー主宰の齋藤精一さんに聞いた。
「理想のライフスタイルは違う」という気づき
新型コロナウイルス感染症の影響で、人々はこれまでとは違う暮らしを強いられるようになった。齋藤さんは、コロナ禍における人の意識の変化が、今後の都市のあり方に深く関わると話す。
「今回のコロナによって、人類は『そもそも人間ってなんだろう』『命ってなんだろう』」という、哲学的な問いを突きつけられたように感じています。
これからのあり方について活発に議論されるようになり『ニューノーマル』のような新しい考え方も出てきました。住む場所についても、都会ではなくて郊外で暮らしたいという声も多く出ています。僕自身、神奈川に住んでいてよかったと感じました。
今まで職住近接が良いみたいな流れがあったかと思いますが、今回の件で、子供の教育やワークライフバランスの比重など、それぞれの家庭の事情や価値観により、理想とするライフスタイルは違うことがわかったのです。
東京一極集中だった流れが変わり東京から人が離れると、今度は東京が東京じゃなくなるのではと思います。すでに大規模な都市開発が行われているので、今からブレーキをかけてももう止められません。逆に、建物をどう使っていくかを考え始めるのだと思います」

写真提供:アフロ
これまで、日本の都市部、特に東京では大規模な都市開発が進められてきた。新たなビルが次々と建てられ、都市への密集が価値になっていたともいえる。withコロナの時代となり人々の生活が変わったことは、都市開発のあり方が見直されるきっかけになる。
「2020年に新型コロナウイルス感染症が流行しなければ、いけいけどんどんで開発を進める状態が続いたと思います。新しい施設が建設され、メディア企業などはこれまでとは違うドメインの事業者が場を持つようになっていた。ところが2ヵ月、3ヵ月とこの状況が続く中で『今までランナーズハイだったな』と気づく人が出てきています。
僕も大阪万博に関わらせてもらっている中で、国際的な大規模イベントのあり方や、国の機能を再構築しなければならないと感じています。近年のオリンピックは、放映権、ビジネスのための側面が強かった。そこから、いろんなものを削ぎ落として、そもそもオリンピックとはどういう意味があるものかを考えなければならない。オリンピックの延期は、本来の心拍数に戻す大きなきっかけになったと思います」
都市の記憶がシビックプライドを生む
これまでの日本の都市開発やまちづくりについても、欧米でいうところのシビックプライド(Civic Pride)を大切にする側面がなかった、と齋藤さんは指摘する。
「愛のないコミュニティベースのまちづくりになってしまっていることが、日本の都市開発の失敗ではないかと感じています。
例えばニューヨークのブルックリンに住む市民は、自分たちの町のことが大好きなんですよね。地ビールを作ったり、音楽シーンを盛り上げるための施設をみんなでお金を出し合って作るなど、いわゆるシビックプライドがあるんですよね。
一方で、日本の最近の都市開発は、不動産ディベロッパーによる競争の側面が強い。国家戦略特区のガイドラインに沿って文化施設やインキュベーションセンターを作ると容積率を高められるので、各ビルに同じようなスペースができました。だけど、本来そこにコミュニティがあったわけではないので『仮面コミュニティ』みたいなものが増えてしまった。結局、最初に愛がないから、何も生まれない。
シビックプライドとは、スポーツチームがあるということかもしれないし、街並みが守られているということかもしれない。いずれにせよ、日本でも『愛があるコミュニティベースのまちづくり』が必要だと感じます」

ブルックリンの町並み 写真提供:アフロ
齋藤さんは、「1964年の渋谷の街を保存する」というプロジェクト(1964 TOKYO VR(外部サイト))を行ってきた。これは、日本の都市開発に対する警鐘でもあった。
「1964 TOKYO VRは、土地の記憶を残したいと思って始めたプロジェクトです。
東京は、金太郎飴のようなどこを切り取っても同じような都市開発が進んでいます。それは、耐震性などの問題で、昔からあったものをリノベーションするより新しいものをつくるほうがお金がかからないという実情もあると思いますが、開発が行き過ぎると、本来その場所に何があったかわらかなくなってしまうんです。
例えば、渋谷って宇田川と渋谷川という川が流れていて、新しくできたスクランブルスクエアの下にも流れているのですが、それを知らない人も多い。このままでは、昔どんなコミュニティがあり、渋谷で何が起きていたかの記憶も失われてしまう。せっかくオリンピックのような契機があるので、わかりやすく64年ぐらいの渋谷の様子と2020年の様子と比較できる様にした方がいいのではと始めたプロジェクトです」

1964 TOKYO VR
今後の都市開発では、土地の記憶を継承することは必要十分条件の一つ。その場所である意味や、そこで人間が生活することの意味を問い続けることで、都市の進むべき方向が見えてくる。
ニューヨーク市は、土地の記憶を残すような都市計画をしている。例えば、スラム化していた旧工場を耐震補強を施し残すことにした。建物を残すことで記憶を継承すると、その記憶を拠り所にシビックプライドが培われる。
コロナでの気づきが、日本の土地に対するスタンスの変化につながると齋藤さんは話す。
「今回のコロナの影響でステイホームする中で、家の周りの場所性に気づいた人も多いのではないでしょうか。家の周りを散歩して、こんなお寺があったんだとか、こんな花が咲くんだという気づきです。それが見えたのであれば、場所性を何かしらの方法で残した方がいいと思います。それは、場所を残すのか、それとも記憶としてデータベースで残すのか、表現としてはいろいろあります。コロナで家にいることを余儀なくされて苦しかった反面、気づけたことはたくさんあるんじゃないかと思います」
「ニューヨークの事例の良し悪しはあると思いますが、行政と民間が対話しながら土地と人間生活への解像度を高めていくのが、これからのスーパーシティ、スマートシティのあり方になるといいなと思います」

写真提供:アフロ
問いかけから始まる都市開発
我々は今後、新しい都市のあり方を考え直し、設計し直す必要がある。この状況は、これまでとは違う都市開発を実現するチャンスとも言える。いま必要なことを、齋藤さんはどう捉えているのか。
「我々はもう一度自分自身を見つめ直し、理想のあり方を再度定義し直すことが必要だと思います。そのためには、大人が子どもにするような、今何がやりたいの?将来何になりたいの?どんな生活がしたいの?どこに住みたいのか?といった問いを、自分自身に投げかけ、考え直すことをやってみると良いでしょう」
「これまでは、ランナーズハイ的に周りばかり見て走ってきましたが、これからは良い意味でスローダウンするべきだと思います。そのうえで、自分自身を見つめ直す際は、これまでの概念や方程式に捉われてはいけません。新しい発想で自分自身のあり方を再定義することが必要です。それができれば、もしかすると、オリンピックという概念や地元で行われてきたお祭りという概念自体も変わったり、元に戻ったりするかもしれません。
個人的には、先人が何をやってきたかということにも興味があります。先人が必ずしも正しいとは限りませんが、続いてきたのであれば何かしらの理由があるだろうと感じます」
アートの可能性「対話」と「最初のDo」
齋藤さん自身、建築で培ったロジカルな思考を基に、アート・コマーシャルの領域で立体・インタラクティブの作品を多数手がけてきた。自分自身を見つめ直す手段として、アートの重要性がますます増してくると、齋藤さんは熱を込めて語る。
「メディア・アートは社会を写す鏡のようなものです。例えばとある道具をこんな風に使えばこうなるんじゃないか、といった議論の火種を作ってくれる素晴らしさがあります。
自分は好きか嫌いかなど考えることを通して、自分と対話するための装置でもあるのです。妄想や構想、意見を自分の鏡としてアートに昇華することをいろんなところでもっと大事にしてほしいと感じます。
また、アートは失敗前提であり、そもそも失敗という概念がありません。正解を作らないと生き残れない経済社会の中で、自由に発想して自分と向き合うために、アートだけでなくて美術全般の思想が今の時代に本当に必要だと思います。私自身も、主催した『Staying
TOKYO』という新しいイベントを通して、自分自身が何を学び、何を共有することができるのか、発見し直していました」

『Staying TOKYO』
画像提供:ライゾマティクス
さらにアートは、思考を実現する「最初の手段」にもなるという。
「新しい取り組みを始める際のPDCAで言うところの最初のD(行動)がアートでも良いと思います。これまでも実験的にやってみようというときによく、デザイン思考とかクリエイティブ思考と言われてきました。その、いわば1周目のDを回すために表現の力を使って、感性に訴えかけるものをつくることは大事だと思うのです」
遠い未来と近い未来を同時に描く
コロナを乗り越え、日本社会がよりよい未来をつくるために今何が必要なのか。齋藤さんは「構想」の先にあるものが、日本の成長戦略に必要だと話す。
「構想だけでなく、実装する、ということが重要だと考えています。ステイホーム期間中、ソサエティ5.0や今までの未来都市計画に関する政府の戦略資料を大量に読んだのですが、構想ばかりなんですよね。スマートシティも構想です。これからは、構想ばかりするのではなく、現実を見て実装する必要があります。
コロナの影響で、良くも悪くもデジタル化の動きは生まれています。例えば、政府系の会議をオンラインでやるようになったことなど、小さいことですが大きな変化だと思います。これまで対面で会いたいといっていた人たちも、リモートでやらざるを得ない状況になった。その結果、インターネット回線やサーバー環境の貧弱さも浮き彫りになり、インフラを整備しようという動きが生まれたことは大きな変化です。
デジタル化は言い換えるとユニバーサルブロードバンド。つまり、インターネットで全てがつながることです。若い頃にGoogleすらなかった時代のインターネットに触れた身としては、インターネットって魔法みたいな感覚がずっとありましたが、ようやく本当の意味でのインフラになってくるのかなと思います。
それが最終的には都市のスマート化だったり、安心安全・最適快適のまちづくりにつながります。構想ではなく、都市レベルでの実装がこれから進んでいくでしょうし、逆に実装が進まないまちは置いてかれると思いますね。
今こそクリエイティブアクションが必要なんです。否定するわけではありませんが、デザインシンキングなど思考するだけで止まってしまった部分も大きかったと思います。思考ばかり進化して、「SDGs2.0」みたいなことを言い出す人もいます。
こんな状況下でも、未来都市会議の中では5Gの次の通信規格6Gの話がされていたりします。それも大事な話ですが、今するべき話なのか疑問もあります。国も、都市も、実装してから次に進むという成長戦略に変わっていかなければと思います」
それを実践するために、未来を捉える時間軸を変えてみる。齋藤さんは半年ほど前から、あえて『未来』という言葉を使わないようにしていたそうだ。
「未来という言葉を否定しているわけではありませんが、構想ばかりの世の中で未来というのは少し遠過ぎて、明日自分が何をすればいいのか見えづらくなるなと感じていたからです。『未来は明日の連続である』ということを強調してきました。明日の連続の未来を考えるには、なるべく不確定な要素を排除し、確実に起こり得る未来を考えることが大事だと。
近い未来を考えるときは、今あるものを寄せ集めて何ができるかを考えています。例えば10年後に訪れる6Gの世界なんて誰も知りません。そんな、1個でも不明確な要素が入ると僕は近い未来ではないと思うんですよね」

齋藤さん
一方で、「遠い未来」を考えるときには100年の時間軸で考える。それが齋藤さん流でもある。
「現実レベルで未来を考えていると、今考えられる技術、製品、サービスの中で、突拍子も無いものが出てくる確率って非常に低いと思うんですよね。小さかったものが大きくなったり、遅かったものが早くなる進化は当たり前のように訪れると思いますが、それ以上のものが出てこない。
最近は、バックキャスト的に自分の中で想像し得る最大限遠い未来を同時に考えることを強く意識しています。その思考が、今の時代にすごく大事な気がします。
近い未来は解像度が高く、遠い未来は、いわば妄想ですよね。狂っててもいいから妄想することを、僕なりには大事にしています」
価値観やライフスタイルを見直すことは、都市のあり方に限らず、国のあり方そのものまで考え直すことにつながる。今この時期、これまでの認識を疑うことが、人間生活を中心としたあるべき未来にとって大事なのかもしれない。
- 齋藤精一
-
ライゾマティクス・アーキテクチャー主宰
建築デザインをコロンビア大学建築学科(MSAAD)で学び、2000年からNYで活動を開始。2006年株式会社ライゾマティクス設立。16年からライゾマティクス・アーキテクチャー主宰。建築で培ったロジカルな思考を基に、アート・コマーシャルの領域で立体・インタラクティブの作品を多数作り続けている。2020年ドバイ万博日本館クリエイティブアドバイザー。2025年大阪・関西万博People's Living Lab促進会議有識者。
- 編集・文:株式会社ドットライフ
- 「another life.」という個人のストーリーにフォーカスした媒体を元に、各種サービスを展開。1,000人以上のインタビューで磨かれたノウハウを活かして人のストーリーを引き出し、伝わりやすい表現に整え、共感されるコンテンツを生み出す。
07
コロナとどう暮らす?
Build Back Better
-
- 齋藤精一インタビュー
- withコロナ時代、都市はどう変わる? 人間の延長上にある都市づくりへ
【#コロナとどう暮らす】 - 2020.06.23.Tue
-
- 中野信子インタビュー
FQ×文化放送 連携企画第六弾 - 緊急事態、人々の心に起きていること
【#コロナとどう暮らす】 - 2020.06.25.Thu
- 中野信子インタビュー
-
- 夏野剛インタビュー
- 夏野剛「リーダーの決断で産業構造を再編すべき」
【#コロナとどう暮らす】 - 2020.07.03.Fri
-
- 安宅和人インタビュー
- 安宅和人・新しい未来を作るために、5000年後の目線で今を考える
【#コロナとどう暮らす】 - 2020.07.13.Mon
-
- 田坂広志インタビュー
- 田坂広志・パンデミックの未来は、「デュアルモード社会」にシフトせよ
【#コロナとどう暮らす】 - 2020.07.15.Wed