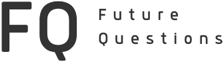2018.11.14.Wed
若きデザイナーと研究家
昆虫食を「未来の一般食」にする
人口増加による食糧危機が迫る中、「救世主」と期待されているのが昆虫食だ。タンパク質などの栄養が豊富で、大量飼育も可能。欧州ではすでに昆虫食ビジネスが広がっている。昆虫は苦手という人も少なくないが、昆虫食の外見と味を改善し、「未来の一般食」にしようと奮闘する人たちを取材した。 (写真:ズッキーニ、パプリカ、さつまいも、パクチーの中央に盛られているのはイナゴ)
2050年、世界人口は現在の76億人から98億人まで増加すると予測されている。各国で食糧が不足し、食料自給率わずか38%で世界最大の食料輸入国の日本も、大きなピンチを迎える。
その「救世主」として期待を集めるのが昆虫食だ。FAO(国連食糧農業機関)は2013年、食糧危機の切り札として「昆虫食」を推奨するリポートを発表した。昆虫はタンパク質やビタミン、鉄分などが豊富で、採集も容易であるため、将来的に牛・豚・鶏に代わる食料になり得るというのだ。
じつは昆虫はすでに東南アジア、アフリカ、中南米などを中心に世界20億人が食べている。種類はコガネムシなどの甲虫類や毛虫・芋虫類など1900以上にのぼる。
ヨーロッパではフィンランド政府が昨年、食用昆虫の生産と販売を許可し、コオロギを素揚げしたスナック菓子などが店頭に並んでいる。昆虫料理を扱うレストランも増えてきた。スイスとオランダのジョイントベンチャーは「食用ハエ」を量産する機械の開発を進めているという。

フランスの食用昆虫の養殖会社「Micronutris」(写真:ロイター/アフロ)
欧州連合(EU)も今年1月、一部の食用昆虫の取引自由化に踏み切ったため、今後は各国で養殖に向けた開発が活発になっていくだろう。市場調査会社パーシステンス・マーケット・リサーチは、世界の昆虫市場は2024年までに7億2300万ドル(約820億円)に達すると予測している。

米国カリフォルニアでの昆虫食イベント(2014年5月 写真:ロイター/アフロ)
日本でも昆虫食の研究進む
一方、日本でも「コオロギの量産化」に取り組んでいる人がいる。徳島大学大学院社会産業理工学研究部の三戸太郎准教授と渡邉崇人助教だ。
「コオロギは年間を通じて卵を産み、1カ月半で成虫になるため、大量生産に適しています。タンパク質はコオロギのパウダー100グラムあたり60グラムも含まれているんですよ」(渡邉助教)
大学内に温度管理のできる農場があり、そこで約10万匹を飼育している。すだちや椎茸をエサにすると、風味が増すこともわかった。今年度中にも大学発のベンチャーを起業し、さらに量産化したいと意気込んでいる。

温度管理をしながら衣装ケースの中でコオロギを飼育(写真提供 渡邉助教)
また山口大学大学院創成科学研究科(農学系)の井内良仁准教授は、バッタ類には体重増加と脂肪蓄積を抑える、いわゆるメタボを予防する成分があるとみて、研究を進めている。
「バッタの糞を湯に溶かして飲んでも、緑茶と同じようなメタボ予防の効果が得られる可能性があります。昆虫は研究の歴史が浅く、大きな可能性を秘めています」
全国的に食べられていた昆虫たち
世界そして日本で、研究が進む昆虫食。その重要性は理解しつつも、まだまだ昆虫食=ゲテモノのイメージを持っている人も少なくないだろう。かくいう私も同様で、お笑い芸人が罰ゲームで食べる映像をつい思い浮かべてしまう。
そんなイメージを払拭してくれる美味しい昆虫食はあるのか?そもそも日本に何種類ぐらいあるのか?昆虫料理研究会代表の内山昭一さん(68)を訪ねてみた。

プロフィール
内山昭一(うちやま・しょういち)/1950年、長野市生まれ。昆虫料理研究家。1998年「世界の食用昆虫展」(多摩動物公園)を機に友人らと昆虫料理研究会を立ち上げて以来、味覚・食感・栄養等、あらゆる角度から昆虫を研究。著書に「楽しい昆虫料理」(ビジネス社)、「昆虫食入門」(平凡社新書)など。
東京・日野市にある内山さんの自宅。
「覚悟したほうがいいですよ」という妻・千里さんの言葉に怯えながら、内山さんの2階の自室にそろり足を踏み入れると、部屋の隅に「黒い何か」が入っていると思われるケースが4箱。おそるおそる中身を尋ねると、内山さんがそれを開く。ガサガサという音と、めまいがしそうな物体......。内山さんはわざわざその1匹をつかんで、我々に見せた。
「マダガスカルゴキブリです」
我々からは悲鳴が漏れ、興奮したゴキブリは「シィィィィィ」と鳴いていた。
内山さんは2種類のゴキブリの他にコオロギを飼育し、カイコやイナゴなど多くの昆虫を冷凍保存している。理由はもちろん、食べるため以外にない。圧倒されながらも、まずは昆虫食の歴史について尋ねた。

昆虫とともに生活
昆虫食は古来、日本でも全国的にあったそうだ。昆虫学者・三宅恒方氏の「食用及薬用昆虫に関する調査」によると、1919年に日本で食べられていた昆虫は55種類。ハチ類が14種と最も多く、ガ類(11種)、バッタ類(10種)、甲虫類(8種)と続く。
「特に関東以北の内陸部では、当たり前のように昆虫が食べられていたようです。イナゴは、お米を作るところだったら全国どこにでもいました。沿岸部の人が魚をとって食べるのと同じように、内陸部の人が栄養価の高い虫を食べることは、ごく自然なことだったと思います」
そんな内山さんは1950年、長野市生まれ。幼少の頃はカイコの蛹(さなぎ)の佃煮が食卓に並んだという。
ところが1960年代に入り、加工や冷凍の技術が発達し、肉や魚が安定的に食べられるようになったこと。また農薬散布によって昆虫が激減したことで、日本の食虫文化は衰退していく。今では長野、岐阜、愛知などに残るのみだ。市販されている昆虫もイナゴ、蜂の子、カイコの蛹(さなぎ)、ざざむし(トビケラ、カワゲラなどの幼虫)などにとどまっている。

蜂(スズメバチ)の子
若い世代で昆虫食が人気
そうした中で、FAOが出した「昆虫食は未来の切り札」という発表。これにより、一般の人の昆虫食への関心が高まっているという。
「毎月、東京都内の料理店で昆虫の調理・試食イベントを開いていますが、ここ数年はほぼ満員です。特に若い男女の参加が増えている。徐々にですが、『食べ物』として見てもらえるようになっています」
ちなみに、これまで100種類以上を食べてきた内山さんの一番美味しかった昆虫料理は、カミキリムシの幼虫の串焼き。続いて、オオスズメバチ前蛹のしゃぶしゃぶ、セミ幼虫の燻製だ。
「幼虫は脂肪分が多いのでいずれもクリーミーな甘みがあります。一方、成虫は筋肉がつくのでさっぱりしていてエビやカニに似た風味です。さなぎはその中間ですね。昆虫はとても種類が多いので、色々な味を発見できることが楽しみです。100gあたりのタンパク質やミネラル含有量は肉や魚よりも多く、保存食、サバイバル食としても最適。今後も魅力を広められればと思っています」

内山さん主催のイベントで作られた「コオロギとカイコ入りのチャーハン」
若きデザイナーの挑戦
色とりどり、さまざまな種類の昆虫がスーパーマーケットに陳列される。飲食店では昆虫を使ったメニューが定番として食べられる――そんな未来を描き、活動している若きデザイナーがいる。高橋祐亮さん(26)。
慶応大学SFCで1年間、食用昆虫の飼育のためのプロダクトをデザインし、東京芸大大学院でも研究を続け、今春修了した。「周囲に『昆虫食のプロジェクトをしている』と話すと、ほとんどの人に変なやつだと思われる」と苦笑いする。

プロフィール
高橋祐亮(たかはし・ゆうすけ)1992年、仙台市生まれ。デザイナー。慶應大学SFCで食用昆虫の飼育のためのプロダクトをデザインし、東京芸大大学院でも制作を継続。今春修了した。昆虫食を「未来の一般食」にするため、日々さまざまなアプローチをしている(撮影:岸本絢)
1年365日、魅力的な昆虫食の探求に余念がない高橋さんだが、意外にも虫嫌い。触ることもできないようなものを、どうやったら食べられるのか? そこに大きな興味があったという。
「FAOのレポートを読んで、『虫が非常食になるなんて嫌だなあ』と思って、僕のように虫嫌いな人が食べられるようになるにはどうすればいいかと考えたのが最初のきっかけです。食糧難の時代になったとしても、やっぱり食事はおいしく食べたいじゃないですか。仕方なく食べるのではなく、視覚やバックストーリーも含めて『おいしい昆虫食を作る』『昆虫食を未来の一般食にする』というのが僕のコンセプトです」
既存のレシピは参考にしない
最初は、昆虫素材の特性をとことん調べた。コオロギやハチなどを揚げたり、茹でたり。どんな処理をしたら匂いが消えるのか、食感はどう変わるのか。昆虫を塩や味噌、塩麴にも漬けて細かく調べあげた。明らかにされていないナゾを解き明かすかのように没頭したという。
その後は、コンセプトに共感する料理家の協力を得ながら、独自のレシピを作っていった。
「一般料理のレシピを参考にすると、エビの代わりに昆虫を使おう、牛肉の代わりにセミを入れてみようとなるので、それはNGにしました。最初に虫を食べてもらい、虫を起点にレシピを考える。この味に何が合うのかを想像し、食材を足して、料理が出来ていくという流れですね」

毎年、研究の成果を「昆虫(食)記」として残している(撮影:岸本絢)
4万2000円の昆虫肉ハンバーガー
高橋さんがこれまで実験的に制作した昆虫食は約30種類。さまざまな昆虫の肉を混ぜることでおいしさを高めた「昆虫肉ハンバーガー」(値段4万2千円)や、コオロギの後ろ脚のごくわずかな肉だけを使ってパテにした「コオロギバーガー」、そして「バンブーワームのココナッツミルク煮込み」など、個性的なものばかりだ。

昆虫肉ハンバーガー(写真提供:高橋祐亮)
料理現場に潜入!
10月末日、高橋さんが新しいレシピの試作をするというので、取材に伺った。使う昆虫は「イナゴ」と「アリの卵」。どちらも昆虫食の本場・タイから輸入した。

料理担当はピリカタント・西野優さん(撮影:岸本絢)

アリの卵(撮影:岸本絢)

素揚げしたイナゴ(撮影:岸本絢)
外見がミニ白子のようなアリの卵は、ともかく大きい。薬のカプセル大ぐらいのサイズだ。一方のイナゴはクリッとした目や立派な後ろ足の幾何学模様が、こちらは一切求めていないのに「虫です!」とグイグイアピールしてきて、ちょっぴり抵抗があった。
調理を担当したのは、自然の食材を活かすのが得意な料理家・西野優さん(ピリカタント)。高橋さんから味をヒアリングして、マッチしそうな食材を用意してきたという。イナゴは素揚げした後、にんにく、しょうが、山椒の甘辛いタレをからめて、野菜で囲む。1時間弱で完成した。
素揚げした段階で試食したイナゴは、香ばしさの一方で味わったことのない独特の風味があった。「完成品」では、そこに山椒の香りがきいたタレがからみ、えも言われぬうまみとなっていた。タレがからんでいるので、過剰な"虫アピール"も緩和されている(※料理写真はタイトル画像として使用)。
一方、アリの卵は、ブルガリアで食べられるという塩気がきいたヨーグルトソースに散らして。色彩豊かで美しい出来上がりで、こちらも昆虫がいることを忘れそうになる。
高橋さんも「レギュラーメニューに加えたい」と興奮するほど、素晴らしかった。卵のプチッと弾ける食感とまろやかさが、ヨーグルトの酸味と塩気、玉ねぎの辛み、イチジクの甘みとあわさって......(以下説明不能)。あまりの美味しさに、筆者も一皿食べてしまった。

「アリの卵のヨーグルトソース」。マリネした赤玉ねぎ、カリフラワー、レモン、イチジクの彩りが美しい(撮影:岸本絢)
美しく、美味しくデザインされた昆虫料理は、インスタグラムを代表とするビジュアル文化で育つ若者からも支持を得られそうだ。
世界に広まるためのカギ
昆虫食の一般化に挑む高橋さん。今後、世界に根付くためのカギを聞いた。
「1つは簡略化しないことだと思います。今、世の中に出ている昆虫食の多くは、粉にしたりミンチにしたりしたもの。確かに昆虫に抵抗がある人たちは、そうした形のほうが食べやすいかもしれませんが、昆虫食を文化にするためには、素材をそのまま生かさなければなりません。例えば、お酒に合う食べ物って、単体だと苦かったりしますよね。単体ではマイナスでも、何かと合わさることでプラスに転換したりします。昆虫の形状や匂いを、あえて生かすアプローチが必要だと思います」
もう1つが、おいしくて安定供給できる昆虫を生み出すこと。野菜や家畜と同じように、昆虫も品種改良を重ねる必要があるというわけだ。
「豚や牛や野菜などは、長い歴史の中でゆるやかに遺伝子改変がなされてきました。しかし、昆虫は大昔からほとんど変わりません。質の高いものを育てようという人や企業が増えることも大事だと思います」
食糧難の時代を見据え、世界は昆虫食の可能性を模索している。2050年、約30年後の日本の食卓に昆虫は乗っているのだろうか。それはどのように売られ、どのように食べるのだろうか。高橋さんの挑戦に今後も注目したい。

タガメをジンに漬けた「タガメジン」。高橋さんと京都のバーが共同制作した。青りんごのような香りが特徴(撮影:岸本絢)
- 取材・文:青木美帆(あおき・みほ)
- 1984年、山口県生まれ。フリーライター兼編集者。スポーツ専門誌の編集者を経て、独立。バスケットボールをメインに、「スポーツと食」、「食と体づくり」などのテーマで取材を行っている。